「おちょやん」の2週目で、千代の奉公先「岡安」に、「天海(てんかい)一座」がやってきますが、この頃喜劇界で日本一と言われていたのが須賀廼家万太郎(すがのやまんたろう)が率いる「万太郎一座」でした。
須賀廼家万太郎のモデルと思われる曾我廼家五郎(そがのや ごろう)について調べてみました。
お話の中では板尾創路さんが演じています。
目次
【おちょやん】須賀廼家万太郎のモデルは?
須賀廼家万太郎のモデルと思われる曾我廼家五郎(そがのや ごろう)さん ↓
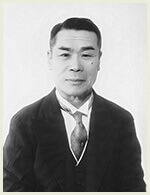
引用:https://www.shochiku.co.jp/shinkigeki/cast/meiyu/
曾我廼家五郎がモデルだと思われる理由
須賀廼家万太郎は、「須賀廼家万太郎一座」を率い、ずば抜けた観客動員数を誇る、喜劇王の役どころです。
大正から昭和にかけての喜劇王と言われ、「おちょやん」に出てくる「鶴亀家庭劇」のモデル「松竹家庭劇」は、「曽我廼家五郎劇」を超えようと奮闘しました。
そのようなことから、曽我廼家五郎が須賀廼家万太郎のモデルと考えられると思います。
以下、曽我廼家五郎の経歴を見ていきます。
喜劇王・曾我廼家五郎の経歴について
曽我廼家五郎の本名は和田久一で、1877年(明治10年)に大阪堺の宿院町に生まれました。
13歳の時、母とともに丁稚奉公に大阪に行きます。
最初、歌舞伎(かぶき)の中村珊瑚郎(さんごろう)の一座に入り中村珊之助として初舞台を住みます。
大阪福井座で中村時蔵(後の3代目中村歌六)の弟子の中村時代にのちの曾我廼家十郎と出会います。二人は当時大阪歌舞伎の売れない役者でした。
珊之助から五郎と改名し、十郎、曾我廼家一満と共に「笑わせる芝居」の創立を発起、日露戦争が始まった1904年(明治37)大阪・浪花座(なにわざ)で「曽我廼家喜劇」を旗揚げしました。
二人が目指したのは、しっかりした脚本と芝居で笑わせる新しい芝居でした。
道頓堀の浪花座で旗揚げ公演は、五郎が脚本を書いた「無筆の号外」という芝居でした。
洋食屋の開店チラシを新聞の号外と勘違いした人々が、ライスカレーやビフテキなどの文字を敵国ロシアの人名だと思い、洋食屋に押しかける、という話で、大うけしたそうです。
後に五郎と十郎は方向性の違いから袂を分かち、十郎が1925年に亡くなると、五郎は「曽我廼家五郎劇」を率いて喜劇王として君臨します。
後のエノケンやロッパも五郎を先生と呼んでいたそうです。
チャップリンが来日した時には五郎を訪問し、新聞に写真入りで載りました。
浪花千栄子が参加した「松竹家庭劇」も「曽我廼家五郎劇」には太刀打ちできなかったと言います。
曾我廼家五郎は大正から昭和へかけて日本の喜劇王として君臨し、既成の歌舞伎や新派に対し「喜劇」というジャンルを開拓しました。
五郎はまた、一堺漁人(いっかいぎょじん)という筆名で1000種を超える脚本も書いたそうです。
晩年は喉頭癌で声が出なくなりましたが、それでも道頓堀中座の舞台に立ち続け、1948年に71歳で亡くなりました。
死後の1948年12月に、中座で松竹新喜劇が結成されたという事です。
岸和田にゆかり
曽我廼家五郎は、大阪の岸和田市にゆかりがあるそうで、岸和田市立図書館には収蔵物もありました。
岸和田図書館が発行している「岸和田発見③岸和田ゆかりの人」にも載っています。
曽我廼家五郎自身は堺の宿院町の生まれでしたが、お父様が岸和田の稲葉町の方だったようです。
「おちょやん」での役どころ
「おちょやん」で須賀廼家万太郎役は板尾創路(いたおいつじ)さんが演じています。
板尾創路が演じる
板尾創路(いたおいつじ)さん ↓

引用:映画.com
板尾さんは、吉本興業のタレント養成所NSC大阪を卒業後、蔵野孝洋(ほんこん)とお笑いコンビ「130R」を結成。
俳優としても活躍し、NHK連続テレビ小説「まれ」(2015)、連続ドラマ「沈まぬ太陽」(2016)などに出演。
2017年には又吉直樹の芥川賞受賞作の映画化「火花」で監督もしています。多才な方ですね!
須賀廼家万太郎の役どころ
曾我廼家五郎がモデルの須賀廼家万太郎は、「須賀廼家万太郎一座」を率い、ずば抜けた観客動員数を誇る、喜劇王の役どころです。
🎍#おちょやん 登場人物紹介🎍
須賀廼家(すがのや)万太郎🍵#板尾創路
板尾さんが演じる万太郎さんは、ずば抜けた観客動員数を誇る喜劇王。
まだテレビのない時代なのに、大阪だけでなく東京でも人気者!すごいっ!👏👏👏
\放送開始まであと7日/
#11月30日放送開始 pic.twitter.com/hXBdgO7Dbn
— 朝ドラ「おちょやん」放送中 (@asadora_bk_nhk) November 23, 2020
大阪だけでなく、東京でも人気は抜群で、千代や一平たちは、万太郎を超えることを目標に奮闘することになるそうです。
12月10日には、急死した渋谷天外のお葬式に、弟子たちを引き連れてやってきて、一芝居打って帰りました。
このようなことが実際あったのかは分かりませんが、さすが喜劇王、どんな時にも喜劇の精神を忘れないのですね。
葬儀のシーンに関するツイート
葬儀のシーン最高やった~。
喜劇役者の葬式はこうでないとなぁ。
しんみりするのは似合わへんもん。
須賀廼家万太郎さん、めっさカッコよかったわぁ♡
鶴亀座の社長との会話の応酬も洒落が効いてて素晴らしかった。
私はこういう脚本を求めてたのよ。#朝ドラ #おちょやん #須賀廼家万太郎 #板尾創路— ム ス タ ン グ ☆ 3 8(佐々木三八) (@skull_38jp) December 9, 2020
お葬式で色とりどりの紙吹雪、驚きましたね。頭の卵から出てきたように見えましたが、どんな仕組みだったのでしょうか ↓
「人の世は笑えん喜劇と笑える悲劇のよじれあいや」「よじれんのは腹だけにしたいもんやなぁ」須賀廼家万太郎と鶴亀の大山社長のやり取りに座布団一枚!
ところであの紙吹雪は万太郎の脇にしゃがんだ弟子達が一生懸命飛ばしてたのか? #おちょやん— Big✮K31✮ツブヤッキー (@sojo2071ko) December 10, 2020
ポスターの絵が板尾創路さんそっくりですね! ↓
詳しいキャストまだ把握してないけど須賀廼家万太郎←板尾創路というのはわかったw#おちょやん pic.twitter.com/T9izIVYLsl
— バブルですが (@Baburudesuga) December 8, 2020
須賀廼家万太郎、さすが喜劇王ですね! ↓
須賀廼家万太郎は、なぜ芝居小屋で舞台葬してるかの効果と意味を理解した上でやってきて、観客もいないし報酬ももらえんくても「ボケてみせる」笑いを生きる男。で、その後で「全部わかってんっで」言葉にして、煽ってみせる。ライバルがほしいし、後継者もほしいからか? #おちょやん https://t.co/gtWsdri5jV
— 高橋真直 (@t_massugu) December 10, 2020
43話で衣装早変わり
43話では、スーツからふんどし姿、着物への早変わりも披露してくれました。
弟子の役者が脱がせて着せて、万太郎さんは両手を広げて立っていただけですが(笑)
道頓堀のてっぺん、須賀廼家万太郎の公開お着替え🤭 ようわからんけど…すすすごいな… #板尾創路 #朝ドラ #おちょやん pic.twitter.com/3L8PMuJuZM
— 朝ドラ「おちょやん」放送中 (@asadora_bk_nhk) February 2, 2021
仕掛けはこのようになっているようです ↓
着けているのはスナップボタンだとか…
(続き) 「マジックテープですか?」「いえ、スナップボタンです。テープは音がするので」 目立たぬようにていねいに縫い込まれていました。 万太郎さんが動いたときにははずれないよう、でも引っ張ると気持ちよくはずれるように。絶妙な固さでした…衣装さんすごい… #朝ドラ #おちょやん pic.twitter.com/Yq4P62IdTj
— 朝ドラ「おちょやん」放送中 (@asadora_bk_nhk) February 2, 2021
19週で最後の芝居
終戦から3年、千代たちの家庭劇は地方を回って細々と芝居を続けていました。
そんな時に鶴亀社長の大山によって道頓堀に呼び出されます。
大山は「鶴亀新喜劇」を発足させようとしていたのでした。大山が万太郎一座ではなく鶴亀家庭劇を呼んだのは、理由がありました。
万太郎が喉のガンにかかり、声が出なくなってしまったのです。(これは史実と同じです)
そして、最後に千之助と40年ぶりに同じ舞台に立ち、拍手喝さいを浴びて幕が下がると、舞台裏で万太郎は座り込みそのまま息絶えます。(これは史実とは違います)
万太郎のモデル、曾我廼家五郎も声が出なくなっても道頓堀中座の舞台に立ち続けたそうです。本当に芝居が好きだったのですね。
●今までの「おちょやん」や他の朝ドラを一定期間無料で観る方法があります ↓
NHK朝ドラの見逃し動画を無料でパソコンやスマホから観る方法!登録の注意点も!
まとめ
今回は、須賀廼家万太郎のモデルと思われる曾我廼家五郎(そがのや ごろう)について見てきました。
喜劇というジャンルを作り上げた第一人者ですね。
板尾さんの演技が素晴らしかったです!
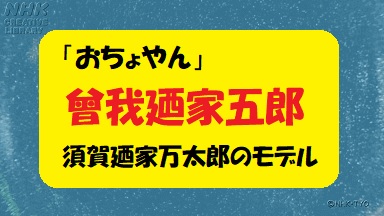
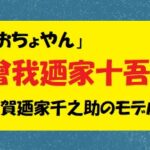
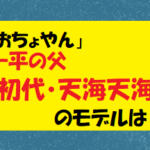
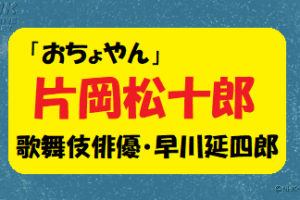

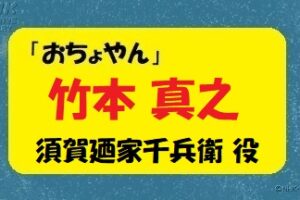
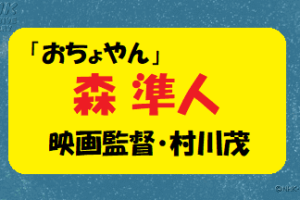
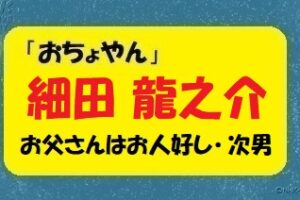
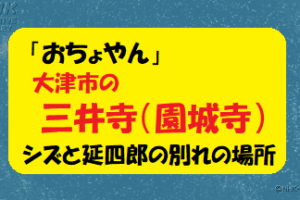
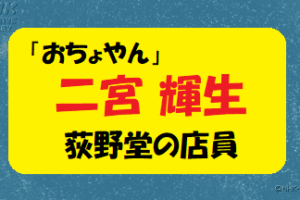
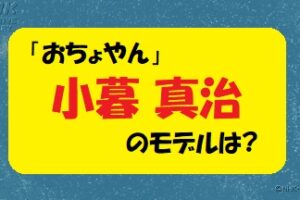
コメントを残す